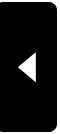2009年03月14日
電子カルテの特徴と導入例・・・「「CIMA Chart」の機
才ノヽ∋―_φ(゜▽゜*)♪
今日は、寒くなりそう?~{{ (>_<) }}
何回か、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、お役に立ちますか?
さて、今回は、「CIMA Chart」の機能(2)についてです。
診療所用電子カルテ「CIMA Chart」の受付・会計における機能を紹介します。
1、新しい患者の登録や、患者受付の操作を、患者保険画面で行います。受付を済ませてから、バイタルや問診を入力することもできます。入力したデータは、端末全てに表示されるので、待合室にいる患者の状況などが、どこにいても把握することができます。
2、簡単な操作によって、会計処理を行うことができるので、患者の待ち時間が短くなります。また、会計処理と同時に、その患者のレセプトが自動的に作成されるので、月末を待つことなくレセプトが可能です。
次に、レセプトに関する機能を紹介します。
1、レセプト画面を、全ての端末から表示することが可能です。カルテボタンを押せば、その患者のカルテ画面が、瞬時に表示されます。また、院外の処方内容も表示できるので、レセプト点検作業を効率的に行うことができます。
病名ボタンによって、病名を登録すれば、同時に結果がレセプトに表示されます。問題点は、付箋部分に記したり、レセプト上に色付けしたりすることで、明確にわかるように表現することが可能です。
2、レセプトの点検を行うと、いつ誰が点検したかが記録されるので、全体的な進行状況を把握することができ、何度も同じレセプトを確認することがなくなります。また、病名チェックでは、初診や再診の日付が適合しているか、病名に対する薬剤が適当か、病名に対する検査が適しているかをチェックしてくれます。
参考になったかな?
では、また!
今日は、寒くなりそう?~{{ (>_<) }}
何回か、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、お役に立ちますか?
さて、今回は、「CIMA Chart」の機能(2)についてです。
診療所用電子カルテ「CIMA Chart」の受付・会計における機能を紹介します。
1、新しい患者の登録や、患者受付の操作を、患者保険画面で行います。受付を済ませてから、バイタルや問診を入力することもできます。入力したデータは、端末全てに表示されるので、待合室にいる患者の状況などが、どこにいても把握することができます。
2、簡単な操作によって、会計処理を行うことができるので、患者の待ち時間が短くなります。また、会計処理と同時に、その患者のレセプトが自動的に作成されるので、月末を待つことなくレセプトが可能です。
次に、レセプトに関する機能を紹介します。
1、レセプト画面を、全ての端末から表示することが可能です。カルテボタンを押せば、その患者のカルテ画面が、瞬時に表示されます。また、院外の処方内容も表示できるので、レセプト点検作業を効率的に行うことができます。
病名ボタンによって、病名を登録すれば、同時に結果がレセプトに表示されます。問題点は、付箋部分に記したり、レセプト上に色付けしたりすることで、明確にわかるように表現することが可能です。
2、レセプトの点検を行うと、いつ誰が点検したかが記録されるので、全体的な進行状況を把握することができ、何度も同じレセプトを確認することがなくなります。また、病名チェックでは、初診や再診の日付が適合しているか、病名に対する薬剤が適当か、病名に対する検査が適しているかをチェックしてくれます。
参考になったかな?
では、また!
2009年03月13日
「「CIMA Chart」の機能(1)」
( ̄´-` ̄)ノヤァ、こんにちは
今日は、どんな一日でしたか?
毎回、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、
さて、今日は、「CIMA Chart」の機能(1)について考えて見ます。
診療所用電子カルテ「CIMA Chart」の、診察における機能を紹介します。
1、「SOAP形式」によって、短時間で入力することができます。また、十分に正常所見を記載することができ、異常所見がはっきりとわかるカルテを作成することができます。画面を使用した入力ツールのテンプレートは、クリニックごとに画面を自由に作成することが可能です。診察する項目については、必ず正常所見として予めチェックしておくと、入力が迅速にできます。また、異常所見は、フォントや色を変えたりすることで、強調することができます。
2、「カルテスタンプ機能」では、所見、処方や検査の指示といった、病状に合わせた入力パターンを登録することができます。また、ボタン1つで、カルテに記載したり、修正したりすることも可能です。
3、処方、診療行為、病名など全てのマスタは、厚生労働省が一般に公開している「レセプト電算マスタ」を起用しています。簡単な操作によって、処方指示や定期処方の指示を行ったり、過去の指示をコピーしたりすることができます。
次は、処置や検査に関する機能を紹介します。
1、看護士が指示を確認して、それを実施したら、指示の確認画面の対象となる部分にチェックを入れると、指示の一覧から削除されて、他の端末でも、その指示が実行されたことを確認することができます。
2、外注検査センターから、フロッピーデスクで結果を入手することで、カルテにワンタッチで結果データを登録することができます。検査歴画面で、結果を時系列で表示することができます。また、経過表や検査の結果から、グラフを簡単に作成できます。さらに、作成したグラフを、カルテに添付したり、患者にコピーして渡したりすることができます。
3、検査画像の取り込みも可能で、時系列によって表示できたり、患者さんにコピーして渡したりすることもできます。
今日の話の感想は?
お役に立ちましたか?
それでは、また!
今日は、どんな一日でしたか?
毎回、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、
さて、今日は、「CIMA Chart」の機能(1)について考えて見ます。
診療所用電子カルテ「CIMA Chart」の、診察における機能を紹介します。
1、「SOAP形式」によって、短時間で入力することができます。また、十分に正常所見を記載することができ、異常所見がはっきりとわかるカルテを作成することができます。画面を使用した入力ツールのテンプレートは、クリニックごとに画面を自由に作成することが可能です。診察する項目については、必ず正常所見として予めチェックしておくと、入力が迅速にできます。また、異常所見は、フォントや色を変えたりすることで、強調することができます。
2、「カルテスタンプ機能」では、所見、処方や検査の指示といった、病状に合わせた入力パターンを登録することができます。また、ボタン1つで、カルテに記載したり、修正したりすることも可能です。
3、処方、診療行為、病名など全てのマスタは、厚生労働省が一般に公開している「レセプト電算マスタ」を起用しています。簡単な操作によって、処方指示や定期処方の指示を行ったり、過去の指示をコピーしたりすることができます。
次は、処置や検査に関する機能を紹介します。
1、看護士が指示を確認して、それを実施したら、指示の確認画面の対象となる部分にチェックを入れると、指示の一覧から削除されて、他の端末でも、その指示が実行されたことを確認することができます。
2、外注検査センターから、フロッピーデスクで結果を入手することで、カルテにワンタッチで結果データを登録することができます。検査歴画面で、結果を時系列で表示することができます。また、経過表や検査の結果から、グラフを簡単に作成できます。さらに、作成したグラフを、カルテに添付したり、患者にコピーして渡したりすることができます。
3、検査画像の取り込みも可能で、時系列によって表示できたり、患者さんにコピーして渡したりすることもできます。
今日の話の感想は?
お役に立ちましたか?
それでは、また!
2009年03月12日
「「CIMA Chart」導入の感想」
こんにちは
今日は、いい天気ですね!(..)(^^)(^。^)(*^o^)(^O^)ウレシーーー!!
何回か、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、お役に立ちますか?
さて、今回は、「CIMA Chart」導入の感想についてです。
診療所用電子カルテ「CIMA Chart」を実際に導入している、島根県出雲市にある「すぎうら医院」の感想を紹介します。
シーマチャートを導入したことによって、診療や治療、そして会計など、さまざまな面で電子化されて、それがデータとして蓄積されるので、従来では手間のかかっていた業務が、簡単ですばやく行えるようになったそうです。
看護師への指示や処方の指示など、簡単な操作で、カルテへの記入ができますし、スタッフ全員で情報を共有できるので、患者情報が正確に伝達できるようになりました。また、会計やレセプトを行うために必要な機能にも優れているので、開業医にとって重要な仕事の1つである、経営判断にも大いに役立っているようです。
このようなシーマチャートのメリットは、医師やスタッフに、時間的な余裕を与え、患者さんと応対する大切な時間もでき、患者さんに対するサービスの向上を実感しているそうです。
また、シーマチャートの導入により、それまで、事務的にこなしていた仕事が、「患者さんのために」という意識をもって、行うようになったそうです。受付、会計、レセプトを処理するなどの医療事務の業務は、その量を、とにかく事務的にこなさないといけませんでした。膨大な量の書類と、手間のかかる業務に、毎日毎日追われていたそうです。
それが、シーマチャートの導入により、同じ業務をとても簡単な操作で行えるようになり、時間と気持ちに余裕がもてるようになったそうです。また、医師から受ける指示も、より正確に受け入れることができるようになり、従来に比べて、スムーズに業務が進むようになったようです。そして、患者さんの待ち時間も短くなり、とても喜んでもらっているそうです。
皆さんは、今回の「「CIMA Chart」導入の感想」について、どう思いますか?
参考になったかな?
それでは、また!
今日は、いい天気ですね!(..)(^^)(^。^)(*^o^)(^O^)ウレシーーー!!
何回か、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、お役に立ちますか?
さて、今回は、「CIMA Chart」導入の感想についてです。
診療所用電子カルテ「CIMA Chart」を実際に導入している、島根県出雲市にある「すぎうら医院」の感想を紹介します。
シーマチャートを導入したことによって、診療や治療、そして会計など、さまざまな面で電子化されて、それがデータとして蓄積されるので、従来では手間のかかっていた業務が、簡単ですばやく行えるようになったそうです。
看護師への指示や処方の指示など、簡単な操作で、カルテへの記入ができますし、スタッフ全員で情報を共有できるので、患者情報が正確に伝達できるようになりました。また、会計やレセプトを行うために必要な機能にも優れているので、開業医にとって重要な仕事の1つである、経営判断にも大いに役立っているようです。
このようなシーマチャートのメリットは、医師やスタッフに、時間的な余裕を与え、患者さんと応対する大切な時間もでき、患者さんに対するサービスの向上を実感しているそうです。
また、シーマチャートの導入により、それまで、事務的にこなしていた仕事が、「患者さんのために」という意識をもって、行うようになったそうです。受付、会計、レセプトを処理するなどの医療事務の業務は、その量を、とにかく事務的にこなさないといけませんでした。膨大な量の書類と、手間のかかる業務に、毎日毎日追われていたそうです。
それが、シーマチャートの導入により、同じ業務をとても簡単な操作で行えるようになり、時間と気持ちに余裕がもてるようになったそうです。また、医師から受ける指示も、より正確に受け入れることができるようになり、従来に比べて、スムーズに業務が進むようになったようです。そして、患者さんの待ち時間も短くなり、とても喜んでもらっているそうです。
皆さんは、今回の「「CIMA Chart」導入の感想」について、どう思いますか?
参考になったかな?
それでは、また!
2009年03月11日
電子カルテの特徴と導入例・・・「診療所用電子カルテ「CIMA
才ノヽ∋―_φ(゜▽゜*)♪
今日も、花粉が飛んでいますよ~!
朝から、鼻水が。。。☆≡(*。< )
毎回、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、
さて、今日は、診療所用電子カルテ「CIMA Chart」について考えて見ます。
診療所用電子カルテ「CIMA Chart(シーマチャート)」について紹介します。シーマチャートとは、レセプト電算処理や健康診断を行える機能を搭載した、診療所用の電子カルテシステムのことです。それでは、シーマチャートについて簡単に紹介します。
・瞬時に、レセプトやカルテ、会計の画面に切り替えることができます。1システム、診療所で行う業務全体をサポートするので、医師をはじめスタッフも、その便利さを実感しています。
・往診先や自宅でも利用することができます。WEBブラウザを利用して行うWEB型電子カルテなので、インターネットVPNを通じて、往診先や自宅からでも利用が可能です。また、カルテをノートブックに持ち出すことで、ネットワークが遮断される場所にいても、診療を行えます。
・健診データ管理機能が装備されており、特定健診に備えています。健康診断で行う項目に合わせて、健診票を複数作成することができます。また、健診の結果から、その経過グラフを作成して、カルテへ貼り付けたり、簡単な操作でEXCELに出力したりして、健診データを自由に活用できます。
・総合病院とかかりつけ医師のいる診療所が連携したり、診療所と診療所が連携したり、また、国立感染症研究所と連携したりすることで、早期に感染症の流行を察知するなど、医療ネットワークを活用するという先進の電子カルテです。
・医師やスタッフ一人一人が、機能や表示などを使いやすいように、カスタマイズすることが可能です。また、モニターを2つ表示することもできます。さらに、端末のライセンス料は無料なので、端末を必要なだけ追加できます。
また、明日~マタネッ(^ー^)ノ~~Bye-Bye!
今日も、花粉が飛んでいますよ~!
朝から、鼻水が。。。☆≡(*。< )
毎回、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、
さて、今日は、診療所用電子カルテ「CIMA Chart」について考えて見ます。
診療所用電子カルテ「CIMA Chart(シーマチャート)」について紹介します。シーマチャートとは、レセプト電算処理や健康診断を行える機能を搭載した、診療所用の電子カルテシステムのことです。それでは、シーマチャートについて簡単に紹介します。
・瞬時に、レセプトやカルテ、会計の画面に切り替えることができます。1システム、診療所で行う業務全体をサポートするので、医師をはじめスタッフも、その便利さを実感しています。
・往診先や自宅でも利用することができます。WEBブラウザを利用して行うWEB型電子カルテなので、インターネットVPNを通じて、往診先や自宅からでも利用が可能です。また、カルテをノートブックに持ち出すことで、ネットワークが遮断される場所にいても、診療を行えます。
・健診データ管理機能が装備されており、特定健診に備えています。健康診断で行う項目に合わせて、健診票を複数作成することができます。また、健診の結果から、その経過グラフを作成して、カルテへ貼り付けたり、簡単な操作でEXCELに出力したりして、健診データを自由に活用できます。
・総合病院とかかりつけ医師のいる診療所が連携したり、診療所と診療所が連携したり、また、国立感染症研究所と連携したりすることで、早期に感染症の流行を察知するなど、医療ネットワークを活用するという先進の電子カルテです。
・医師やスタッフ一人一人が、機能や表示などを使いやすいように、カスタマイズすることが可能です。また、モニターを2つ表示することもできます。さらに、端末のライセンス料は無料なので、端末を必要なだけ追加できます。
また、明日~マタネッ(^ー^)ノ~~Bye-Bye!
2009年03月10日
「患者が望む医療データ」
おはようございますヽ(^▽^@)ノ
今日は、どんな一日でしたか?
毎回、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、
さて、今回は、患者が望む医療データについて、考えてみよう!
患者にとって、理想的な医療データの在り方とは、どのようなものでしょう。患者には、かかりつけの病院があると思いますが、そこには、自分だけのカルテがあって、面識のある先生がいるはずです。つまり、その医療機関には、自分のデータが存在するということになります。
しかし、現在の医療状況においては、時間がある程度経過すると、記録が残されていない場合があります。久しぶりに、病院を受診すると、事務員から「以前受診されたことがありますか?」と聞かれると思います。「3、4年前にあります。」と答えると、「カルテがまだ残っているか、確かめてみますね」と言われます。3、4年前だと思っていても、実際にはもっと前に受診していたり、カルテが残されていなかったりする場合がよくあります。そうすると、新しいカルテを作ることになります。つまり、この患者の過去のデータはなくなったことを意味し、白紙の状態からまた始めることになります。患者にとっては、昔のデータも含めて、できるだけ記録が残されている方が良いに決まっています。医療データというのは、長期間保存されることが理想的なのです。
患者は、医師が告げた病気が、本当に自分がかかっている病気なのか、手術は本当に必要なのか、という疑問を持ち、別の医師の意見も聞いてみたいと思うかもしれません。しかし、そのようなことを、患者が自分から切り出すことは、かなりの抵抗があると思います。
また、旅行などで、かかりつけの病院に行けなくても、現地の病院で自分のデータを提供できるように、データのコピーを自分で保持しておきたい、と考えている患者も多いでしょう。医療データというのは、患者自身のデータなので、患者自らの管理下にも存在することが望ましいのです。
今日は、コレでおしまいっ。
今日は、どんな一日でしたか?
毎回、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、
さて、今回は、患者が望む医療データについて、考えてみよう!
患者にとって、理想的な医療データの在り方とは、どのようなものでしょう。患者には、かかりつけの病院があると思いますが、そこには、自分だけのカルテがあって、面識のある先生がいるはずです。つまり、その医療機関には、自分のデータが存在するということになります。
しかし、現在の医療状況においては、時間がある程度経過すると、記録が残されていない場合があります。久しぶりに、病院を受診すると、事務員から「以前受診されたことがありますか?」と聞かれると思います。「3、4年前にあります。」と答えると、「カルテがまだ残っているか、確かめてみますね」と言われます。3、4年前だと思っていても、実際にはもっと前に受診していたり、カルテが残されていなかったりする場合がよくあります。そうすると、新しいカルテを作ることになります。つまり、この患者の過去のデータはなくなったことを意味し、白紙の状態からまた始めることになります。患者にとっては、昔のデータも含めて、できるだけ記録が残されている方が良いに決まっています。医療データというのは、長期間保存されることが理想的なのです。
患者は、医師が告げた病気が、本当に自分がかかっている病気なのか、手術は本当に必要なのか、という疑問を持ち、別の医師の意見も聞いてみたいと思うかもしれません。しかし、そのようなことを、患者が自分から切り出すことは、かなりの抵抗があると思います。
また、旅行などで、かかりつけの病院に行けなくても、現地の病院で自分のデータを提供できるように、データのコピーを自分で保持しておきたい、と考えている患者も多いでしょう。医療データというのは、患者自身のデータなので、患者自らの管理下にも存在することが望ましいのです。
今日は、コレでおしまいっ。
2009年03月09日
医師が望む医療データについて
こんにちは(/゜ー゜)゜ー゜)ノ ♪
今日は、いい天気ですね!(..)(^^)(^。^)(*^o^)(^O^)ウレシーーー!!
今日は、医師が望む医療データの医師が望む医療データについて書いてみますね。
医師が望む医療データとは、まず、患者の過去のデータを簡単に確認することができることです。そのためにカルテが存在しているのですが、現在、ほとんどの医療機関で使われている紙カルテは、いくつかの点で不都合が生じます。カルテは年ごとや、数年ごとに更新されて、古いデータが残されていなかったり、カルテ庫とは別の場所に保管されていたりする場合があります。
また、初診の患者を診察する際に、医師にとって都合の良いものは、前に診た医師からの紹介状です。紹介状があれば、短時間でその患者の状態を把握することができます。しかし、ほとんどの場合、患者は別の病院を受診したとしても、新しい病院へ、身体一つで受診すると思います。そのため、医師は、家族の病歴や、それまでにかかった病気、今回受診した理由に関係する病歴を、その患者の記憶を頼りにしながら、問診していく必要があります。
ところが、患者のほとんどが、今までに病院に何回かはかかったことがあるはずなので、前医での治療の経過やデータの蓄積があれば、これから診察する医師にとって、非常に役立ちます。
逆に、場合によって、医師は、他の医師に患者を紹介する必要が出てきます。これは、現在では、紹介状を書くことで行っていることですが、入院経過が長期間であったり、複雑な病歴であったりすると、紹介状を作成するのも手間のかかるものになります。しかし、明確な情報を伝えるためには、簡単に済ませるわけにはいきません。
どうにかして、カルテの中身を要約して、詳細な紹介状を作成する方法が存在すれば良いのですが、現状では、そのような方法はないようです。また、カルテ自体を複製することで、他の医療機関に提供すれば、簡単に多くの情報を把握できるかもしれませんが、この方法では、元のカルテがどれであったのか、分からなくなってしまう可能性が出てきます。
今日の話の感想は?
役に立ちましたか?
今日は、コレでおしまいっ。
今日は、いい天気ですね!(..)(^^)(^。^)(*^o^)(^O^)ウレシーーー!!
今日は、医師が望む医療データの医師が望む医療データについて書いてみますね。
医師が望む医療データとは、まず、患者の過去のデータを簡単に確認することができることです。そのためにカルテが存在しているのですが、現在、ほとんどの医療機関で使われている紙カルテは、いくつかの点で不都合が生じます。カルテは年ごとや、数年ごとに更新されて、古いデータが残されていなかったり、カルテ庫とは別の場所に保管されていたりする場合があります。
また、初診の患者を診察する際に、医師にとって都合の良いものは、前に診た医師からの紹介状です。紹介状があれば、短時間でその患者の状態を把握することができます。しかし、ほとんどの場合、患者は別の病院を受診したとしても、新しい病院へ、身体一つで受診すると思います。そのため、医師は、家族の病歴や、それまでにかかった病気、今回受診した理由に関係する病歴を、その患者の記憶を頼りにしながら、問診していく必要があります。
ところが、患者のほとんどが、今までに病院に何回かはかかったことがあるはずなので、前医での治療の経過やデータの蓄積があれば、これから診察する医師にとって、非常に役立ちます。
逆に、場合によって、医師は、他の医師に患者を紹介する必要が出てきます。これは、現在では、紹介状を書くことで行っていることですが、入院経過が長期間であったり、複雑な病歴であったりすると、紹介状を作成するのも手間のかかるものになります。しかし、明確な情報を伝えるためには、簡単に済ませるわけにはいきません。
どうにかして、カルテの中身を要約して、詳細な紹介状を作成する方法が存在すれば良いのですが、現状では、そのような方法はないようです。また、カルテ自体を複製することで、他の医療機関に提供すれば、簡単に多くの情報を把握できるかもしれませんが、この方法では、元のカルテがどれであったのか、分からなくなってしまう可能性が出てきます。
今日の話の感想は?
役に立ちましたか?
今日は、コレでおしまいっ。
2009年03月08日
今日は現状のカルテについて
( ̄´-` ̄)ノヤァ、こんにちは
今日は暑かったですね。
何回か、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、お役に立ちますか?
さて、今回は、現状のカルテについて、考えてみよう!
医療情報の保存が、どのように行われているかを知るために、病院の外来用のカルテについて見てみます。
現在の病院での様子を思い浮かべてみてください。病院で患者は、まず受付をします。そうすると、その患者のカルテが事務的に見つけ出されて、診察室に持って行かれます。そして、診察の順番が回ってきたら、診察を受けて、医師は診療内容をカルテに記します。患者は、診察や検査の結果などについての説明を受けます。また、採血のデータなどの一部をコピーして貰うこともあるでしょう。診察が終了すると、再びカルテはカルテ庫の中に保管される、という流れが一般的でしょう。
この紙のカルテは、患者1人に対して、1つ病院内に存在する(病院内一カルテ)場合と、内科、外科、眼科などの科ごとに、1つずつカルテが存在する(各科カルテ)場合があり、それは施設によって違います。
「病院内一カルテ」では、内科や外科のそれぞれ医師は、1冊のカルテに診療内容を記載します。それにより、内科の医師は、外科での治療の内容も、安易に把握することができるというメリットがあります。ところが、患者が、同じ日にいくつかの科を受診する場合は、カルテを順次それぞれの科を移動させていく必要があります。そのため、カルテを搬送する時間とコストがかかってしまいます。また、患者にとって、別の科の医師にあまり知られたくない情報なども、知られてしまうことになります。
一方、「各科カルテ」の場合は、例えば、眼科の医師が、内科のカルテ内容を知りたくても、内科へ問い合わせをする必要があり、手間がかかってしまいます。
どちらが優れたカルテかは、一概には結論付けることはできませんが、厚生労働省は、医療過誤を防ぐためにも、患者1人に1つのカルテを勧めています。また、最近では、電子カルテを導入している医療施設もあり、「病院内一カルテ」が実現してきています。
皆さんは、今回の「現状のカルテ」について、どう思いますか?
お役に立ちましたか?
では、また!
今日は暑かったですね。
何回か、電子カルテの特徴と導入例について書いてみましたが、お役に立ちますか?
さて、今回は、現状のカルテについて、考えてみよう!
医療情報の保存が、どのように行われているかを知るために、病院の外来用のカルテについて見てみます。
現在の病院での様子を思い浮かべてみてください。病院で患者は、まず受付をします。そうすると、その患者のカルテが事務的に見つけ出されて、診察室に持って行かれます。そして、診察の順番が回ってきたら、診察を受けて、医師は診療内容をカルテに記します。患者は、診察や検査の結果などについての説明を受けます。また、採血のデータなどの一部をコピーして貰うこともあるでしょう。診察が終了すると、再びカルテはカルテ庫の中に保管される、という流れが一般的でしょう。
この紙のカルテは、患者1人に対して、1つ病院内に存在する(病院内一カルテ)場合と、内科、外科、眼科などの科ごとに、1つずつカルテが存在する(各科カルテ)場合があり、それは施設によって違います。
「病院内一カルテ」では、内科や外科のそれぞれ医師は、1冊のカルテに診療内容を記載します。それにより、内科の医師は、外科での治療の内容も、安易に把握することができるというメリットがあります。ところが、患者が、同じ日にいくつかの科を受診する場合は、カルテを順次それぞれの科を移動させていく必要があります。そのため、カルテを搬送する時間とコストがかかってしまいます。また、患者にとって、別の科の医師にあまり知られたくない情報なども、知られてしまうことになります。
一方、「各科カルテ」の場合は、例えば、眼科の医師が、内科のカルテ内容を知りたくても、内科へ問い合わせをする必要があり、手間がかかってしまいます。
どちらが優れたカルテかは、一概には結論付けることはできませんが、厚生労働省は、医療過誤を防ぐためにも、患者1人に1つのカルテを勧めています。また、最近では、電子カルテを導入している医療施設もあり、「病院内一カルテ」が実現してきています。
皆さんは、今回の「現状のカルテ」について、どう思いますか?
お役に立ちましたか?
では、また!
2009年03月07日
「電子カルテの問題点」
こんにちは
今日は、いい天気ですね!(..)(^^)(^。^)(*^o^)(^O^)ウレシーーー!!
さて、今回は、電子カルテの問題点について、考えてみよう!
病院で診察を受けるたびに、同じような検査をその都度受けて、カルテを作成していると思います。それと同時に、時間も費用もかかってきます。このような経験は、誰でも一度はあると思います。そして、この流れは当然のことだと思っている人がほとんどでしょう。でも、自分のカルテを、必要な時に、自由に利用することができれば、より検査や診察が効率化します。
これを実現させるものとして注目されているのが、「電子カルテ」です。電子カルテとは、手書きで記入していた紙のカルテを、電子システムに切り換えて、データベースにさまざまな情報を記録する仕組みです。
全国の病院や診療所が、ネットワーク化されることができれば、どこの病院などで受診をしても、自分専用の電子カルテを利用できるようになります。同じような検査を何度も受ける必要がなくなり、医療費の抑制にもつながると考えられています。
当初、厚生労働省は、2006年までに、電子カルテを6~7割の医療施設への普及を計画していました。ところが、現状では、普及率が十数パーセント止まっており、計画が実現するのには程遠いようです。
その理由は、現状のシステムの電子カルテは、医療施設において、デメリットの方が多いことが考えられます。例えば、医者は、診察と同時に、パソコンの操作をこなす必要があり、パソコンに慣れていない医者にとっては、ストレスに感じることになります。そのため、診察に集中することができなくなる、という弊害も起きる可能性があります。
しかも、限られた診察時間の中で、ほとんどの時間をキーボードとモニターに向かっていると、患者に向かい合って話す時間が減ります。現在の医療においては、何より、患者と医者のコミュニケーションが重要視されていますが、その流れに背を向けることにもなってしまいます。そうなると、患者からの多くの苦情も予想されます。
いかがですか。
気になることはありましたか?
では、また!
今日は、いい天気ですね!(..)(^^)(^。^)(*^o^)(^O^)ウレシーーー!!
さて、今回は、電子カルテの問題点について、考えてみよう!
病院で診察を受けるたびに、同じような検査をその都度受けて、カルテを作成していると思います。それと同時に、時間も費用もかかってきます。このような経験は、誰でも一度はあると思います。そして、この流れは当然のことだと思っている人がほとんどでしょう。でも、自分のカルテを、必要な時に、自由に利用することができれば、より検査や診察が効率化します。
これを実現させるものとして注目されているのが、「電子カルテ」です。電子カルテとは、手書きで記入していた紙のカルテを、電子システムに切り換えて、データベースにさまざまな情報を記録する仕組みです。
全国の病院や診療所が、ネットワーク化されることができれば、どこの病院などで受診をしても、自分専用の電子カルテを利用できるようになります。同じような検査を何度も受ける必要がなくなり、医療費の抑制にもつながると考えられています。
当初、厚生労働省は、2006年までに、電子カルテを6~7割の医療施設への普及を計画していました。ところが、現状では、普及率が十数パーセント止まっており、計画が実現するのには程遠いようです。
その理由は、現状のシステムの電子カルテは、医療施設において、デメリットの方が多いことが考えられます。例えば、医者は、診察と同時に、パソコンの操作をこなす必要があり、パソコンに慣れていない医者にとっては、ストレスに感じることになります。そのため、診察に集中することができなくなる、という弊害も起きる可能性があります。
しかも、限られた診察時間の中で、ほとんどの時間をキーボードとモニターに向かっていると、患者に向かい合って話す時間が減ります。現在の医療においては、何より、患者と医者のコミュニケーションが重要視されていますが、その流れに背を向けることにもなってしまいます。そうなると、患者からの多くの苦情も予想されます。
いかがですか。
気になることはありましたか?
では、また!
2009年03月06日
「電子カルテのメリット」
おはようございます
今日は、寒くなりそう?~{{ (>_<) }}
さて、今日は、電子カルテのメリットについて、調べてみました。
電子カルテを導入することで、患者にとって、どんなメリットがあるのでしょう。
医療に限ったことではないですが、電子化によるメリットの1つには、情報が共有化されることです。医療においては、診療の情報を、それぞれの部門で共有することで、患者の状態を、各部門で連動して確認することができます。また、検査や投薬のデータも、ひとつに管理されるために、各部署から情報を入手することで、業務をスムーズに行うことができます。
電子カルテは、一目で患者の投薬内容を確認することができるので、複数の診療科での重複投与も、すぐに発見することができます。また、それぞれの部門への検査や投薬などの依頼も電子化されるので、手書きで起こりがちな、転記ミスなどが減り、紙を保存するためのスペースも必要なくなります。
以前に誰かが入力した情報は、部門システムにより、連携して共通で使用できるのもメリットです。システムの連携が実行できれば、誰かが一度入力した情報は、共通して各システムで利用することができるので、入力ミスを起こしたり、手間を省いたりできます。
また、瞬時に、各部署に依頼情報を転送することができるので、指示から実施まで短時間で行えます。例えば、すぐに会計データが転送されるので、診察が終了してから会計まで、待ち時間の短縮が可能になります。
さらに、電子カルテを利用することで、検査データなどを、画像やグラフで、患者が手軽に確認することができるようになります。
今日の話の感想は?
参考になりましたか?
(@゜▽゜@)ノ~~~マタネ-☆
今日は、寒くなりそう?~{{ (>_<) }}
さて、今日は、電子カルテのメリットについて、調べてみました。
電子カルテを導入することで、患者にとって、どんなメリットがあるのでしょう。
医療に限ったことではないですが、電子化によるメリットの1つには、情報が共有化されることです。医療においては、診療の情報を、それぞれの部門で共有することで、患者の状態を、各部門で連動して確認することができます。また、検査や投薬のデータも、ひとつに管理されるために、各部署から情報を入手することで、業務をスムーズに行うことができます。
電子カルテは、一目で患者の投薬内容を確認することができるので、複数の診療科での重複投与も、すぐに発見することができます。また、それぞれの部門への検査や投薬などの依頼も電子化されるので、手書きで起こりがちな、転記ミスなどが減り、紙を保存するためのスペースも必要なくなります。
以前に誰かが入力した情報は、部門システムにより、連携して共通で使用できるのもメリットです。システムの連携が実行できれば、誰かが一度入力した情報は、共通して各システムで利用することができるので、入力ミスを起こしたり、手間を省いたりできます。
また、瞬時に、各部署に依頼情報を転送することができるので、指示から実施まで短時間で行えます。例えば、すぐに会計データが転送されるので、診察が終了してから会計まで、待ち時間の短縮が可能になります。
さらに、電子カルテを利用することで、検査データなどを、画像やグラフで、患者が手軽に確認することができるようになります。
今日の話の感想は?
参考になりましたか?
(@゜▽゜@)ノ~~~マタネ-☆
2009年03月06日
「電子カルテとは」
おはようございます。
今日から、「電子カルテ」について、紹介していきますね!
さて、今回は、電子カルテとはについてです。
「電子カルテ」とは、それまで、こつこつと医師の手書きによって、紙に書かれていたカルテを、電子ベースに置き替えることで、データベース化によって患者の容態などを記すことです。そうすることで、今までの患者の病歴や、投与された薬などが、簡単な操作によって、すぐに検索することができます。そして、今までの状態と現在の状態の共通点や違いなどが、非常に早く判断することができ、診療をスムーズに行うことができるのです。
医療の世界においても、それだけ“IT化”が進んできています。電子カルテを使用することによって、医師は、昔の病歴を知るために、古いカルテをわざわざ探す必要はなく、簡単な検索で、すぐにわかるようになりました。そのため、容態が共通していれば、過去に処方した薬と同じものを投与すればいいのです。また、点滴や注射などについても、過去にどんな薬を使用したかをすぐに知ることができ、すばやく診療を行うことができるのです。それによって、短時間で多くの患者の診療が可能ですし、患者も長い時間待たされることがなくなるのです。
医師の間では、徐々に電子カルテが広まってきています。電子カルテの実用性や便利さは、それだけ医師の心をつかんでいるということです。
ただ、現実には、このような診療を反発に感じている医師もいます。電子カルテは、パソコンを使用していることから、コンピュータウィルスなどに気をつけなければいけません。また、患者の病歴などは個人情報なので、データの流出にも細心の注意を払わなければなりません。
また、明日~マタネッ(^ー^)ノ~~Bye-Bye!
今日から、「電子カルテ」について、紹介していきますね!
さて、今回は、電子カルテとはについてです。
「電子カルテ」とは、それまで、こつこつと医師の手書きによって、紙に書かれていたカルテを、電子ベースに置き替えることで、データベース化によって患者の容態などを記すことです。そうすることで、今までの患者の病歴や、投与された薬などが、簡単な操作によって、すぐに検索することができます。そして、今までの状態と現在の状態の共通点や違いなどが、非常に早く判断することができ、診療をスムーズに行うことができるのです。
医療の世界においても、それだけ“IT化”が進んできています。電子カルテを使用することによって、医師は、昔の病歴を知るために、古いカルテをわざわざ探す必要はなく、簡単な検索で、すぐにわかるようになりました。そのため、容態が共通していれば、過去に処方した薬と同じものを投与すればいいのです。また、点滴や注射などについても、過去にどんな薬を使用したかをすぐに知ることができ、すばやく診療を行うことができるのです。それによって、短時間で多くの患者の診療が可能ですし、患者も長い時間待たされることがなくなるのです。
医師の間では、徐々に電子カルテが広まってきています。電子カルテの実用性や便利さは、それだけ医師の心をつかんでいるということです。
ただ、現実には、このような診療を反発に感じている医師もいます。電子カルテは、パソコンを使用していることから、コンピュータウィルスなどに気をつけなければいけません。また、患者の病歴などは個人情報なので、データの流出にも細心の注意を払わなければなりません。
また、明日~マタネッ(^ー^)ノ~~Bye-Bye!
タグ :電子カルテ